-

会員管理システム

会員管理システム
-
会員管理システムでは、次の機能がご利用いただけます。
・会員情報の照会・更新
・会費納付状況
・会誌発送状況
・パスワード変更
・オンライン名簿・会員検索システム
・オンラインクレジット決済システム
-
会員管理システムでは、次の機能がご利用いただけます。
-

学会を知る
-

イベントに参加する

イベントに参加する
-

活動にふれる

活動にふれる
-
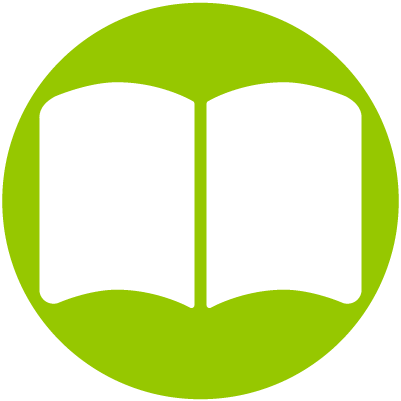
出版物を見る
TOP活動にふれる JACUEセレクション
JACUEセレクション認定図書(最新の認定図書)
JACUEセレクション2023(2022年度認定図書)
①鳥居朋子著(2021)『大学のIRと学習・教育改革の諸相』玉川大学出版部
◇選定理由(抜粋
大学における教学IRの観点から、国内外の特色ある事例を検討し、近年の学習・教育改革の諸相を示している。そして、今後の教学マネジメントやIRの課題について提言している。諸外国については米国、英国、フィンランド、それぞれの高等教育に関する質保証政策と、それに対する特にIR活動を中心とした大学の対応、日本については第3期認証評価で重視されている内部質保証システムにIRを機能させている3大学の事例を紹介している。さらに、コロナ禍により学生の学習環境が大きく変わり、新たな課題が生じている点についても言及している。内外の事例を体系的に論じている点で研究としての質は高い。用語の説明も適切であり、詳細な索引をつけるなど、初学者にも理解しやすい工夫がされている。
②西野毅朗著(2022)『日本のゼミナール教育』玉川大学出版部
◇選定理由(抜粋
本書は著者の博士論文を大幅に加筆修正して刊行されたものである。日本の大学教育の特徴とされてきたゼミナール教育(初年次、専門基礎、専門)のうち、人文・社会科学領域の専門ゼミナール教育に焦点を当て、学習成果の修得と共同体の形成という両側面から、その実態と課題を明らかにすることに成功している。方法としては、歴史的研究、量的研究、質的研究が組み合わせられている。コロナ禍での遠隔ゼミナールの実態にも言及している点や、ゼミナール教育分析を総括しての示唆、提言により想定される読者である高等教育関係者それぞれにも考えさせる構成となっている点は優れている。本書の成果はすでに、中央教育審議会大学分科会「学修者本位の大学教育の実現に向けた今後の振興方策について(審議まとめ)」(2023年3月発出予定)でも引用されており、今後の大学教育の政策・実践に大きな影響を与えることが期待できる。
③大阪大学高等教育・入試研究開発センター編、川嶋太津夫、ジム・ローリンズ、佐々木隆生、ブリギッテ・シテーガ、パク・ピルソン、田川千尋、林篤裕、山下仁司、井ノ上憲司、夏目達也、石倉佑季子著(2022)『未来志向の大学入試デザイン論』大阪大学出版会
◇選定理由(抜粋
本書は、大阪大学の高等教育・入試研究開発センターが2016~21年度に実施した調査研究事業の成果に、新たな論考をくわえてまとめられた。大学入試・高大接続に関する研究開発や、入試専門職の育成研修など、同センターの蓄積が結集され、招聘された特任教授を含めて外国の専門家4名が執筆に参加している。前半では、日本の高大接続改革、大学入試の歴史と現状、外国(米英韓仏)の大学入試が紹介され、その姿が立体的に画かれる。後半では、大学入試の設計、広報、DX活用など入試に関わる幅広い課題が取り上げられ、今般の高大接続改革のなかで注目された「多面的・総合的評価」の手法と課題もまとめられる。末尾の「入試専門家の育成論」は、入試担当者の専門職化を見すえたもので、実践経験が豊富な本センターならではのものである。入試担当者が参考にするべき事項が多岐にわたって記述されていて、その内容は質が高く、一般の読者にもわかりやすい。
JACUEセレクション2022(2021年度認定図書)
①ブルース・マクファーレン著、齋藤芳子・近田政博訳(2021)『知のリーダーシップ:大学教授の役割を再考する』玉川大学出版部
◇選定理由(抜粋
本書は大学教授に求められる知的な役割について再考している。社会における大学の役割は、ICT技術の進展と普及によって低下しており、大学は知的事業体として「創造性と批評能力を高めることに力を注ぎ直す必要がある」と著者は指摘する。そして、現代の大学教授が学内運営や大学評価業務、競争的資金の獲得などに労力が割かれ、知のリーダーとしての役割が弱体化していることを論じている。著者はそれに対して、大学教授は、学問の自由という特権を確保しつつ、果たすべき責務のバランスを取ることで、知のリーダーであるべし、と説く。そのリーダーシップの類型として「知識生産者」、「市民性ある学者」、「知の越境者」、「公共の知識人」の4つを示し、大学教授が現代的役割を果たすことを提案している。この提案は今後の大学教員としてのキャリア開発にも参考になる。大学教員の役割と大学の管理経営を切り分けるような偏狭な議論を乗り越えるために、知のリーダーとしての教授の役割を再評価すべきという本書の主張は、行き過ぎた経営管理主義が進みつつある日本においても傾聴に値する重要な議論である。
②串本剛編(2021)『学士課程教育のカリキュラム研究』東北大学出版会
◇選定理由(抜粋
本書は学士課程教育のカリキュラムについて、専門分野別に必修単位率を規定する要因を大学院進学率、偏差値、ST比を共通独立変数として分析したものであり、日本の大学全体を網羅的に1次資料から統計分析を行った労作であり、今後の学士課程のカリキュラム研究の立脚点となる貴重な研究である。分野別に該当するすべての大学を網羅し、丹念に調べ上げられた客観的なデータにより裏付けられた分析結果からカリキュラム形成の法則を導出することを目的としている。分野毎の章に続いて、科目区分上の「専門科目」の分析、入試難易度別分析、必修単位率分析のまとめの章が置かれており、個別分野のカリキュラムに関心のある読者にも、学士課程カリキュラム全体に関心のある読者にも受け入れられる構成となっている。巻末に先行研究リストがついていることも研究者にとってはメリットである。
③カール・ワイマン著、大森不二雄・杉本和弘・渡邉由美子監訳(2021)『科学立国のための大学教育改革:エビデンスに基づく科学教育の実践』玉川大学出版部
◇選定理由(抜粋
本書は、ノーベル物理学賞受賞者である著者が主導して、コロラド大学(2005年~)とブリティッシュコロンビア大学(2007年~)で実施された、科学教育イニシアティブ(SEI)の概要をまとめた書籍の邦訳である。SEIとは学科を単位とした科学教育の組織的な改善活動である。分野別教育方法研究(DBER)によるエビデンスにもとづいた教授法は、学生の学修成果を画期的に向上させた。本書の記述は、申請のあった学科にSEI予算を配分し、学科長や授業担当教員に新しい教授法の採用を働きかけて、教育の変革を実現して定着させるまでに及び、うまくいかなかった事例とその理由も詳細に述べられている。科学技術分野に限らず、大学で教育改革等に取り組むさいに参照するべき書籍。
④山田礼子・木村拓也編著(2021)『学修成果の可視化と内部質保証:日本型IRの課題』玉川大学出版部
◇選定理由(抜粋
IRとはインスティチューショナル・リサーチの頭文字で、学内の諸活動に関するデータ収集と情報提供をさす。本書は教学IRに関する著者らの研究成果をまとめたものである。IRの実践は学外に発信しにくい性質をもつが、学生調査の結果を学修成果の可視化や内部質保証に活用する方法を中心に記述されている。個別大学および全国規模の学生調査の動向と開発や、学生調査による学生の類型化とともに、他のIRデータとの連結などが扱われ、外部テストとの連結、授業評価の組織的な活用、GPA(学生の成績)と学生調査の連結、ポートフォリオ(文書の形をした学修成果)の分析など、さまざまな分析事例の詳細な説明が含まれる。本書の内容はIR部門のみならず、FD企画部門や、副学長、学部長、事務局長など教学マネジメントに関わる教職員にも有用。
⑤保田幸子著(2021)『英語科学論文をどう書くか:新しいスタンダード』ひつじ書房
◇選定理由(抜粋
本書は、英語による科学論文執筆のガイドブックであるが、類書と異なるのは、副題として「新しいスタンダード」と掲げているように、「書き手の個性や主体性を読み手に伝える」という新しい視点に立っている点である。著者が指摘するように「論文では客観的事実のみを書く」や「一人称の使用や曖昧な表現は避ける」などが標準とされてきた。しかし、近年では書き手の個性や主体性を明示的に示すことが推奨されていることを国際誌の投稿ガイドラインや掲載された論文の計量的分析によって示している。全体は、準備編、基本編、発展篇の3部で構成されており、準備編では、科学論文から主観性が排除されてきた歴史的背景、主観表現の方法を数多くの事例をもとに解説している。基本編では、科学論文のストーリー・テリングという観点から論文の流れを作る「Move」という概念を導入し、情報展開の流れについて解説する。発展篇では、さらに「書き手の個性や主体性を読み手に伝える」文章表現法を具体的な豊富な事例を用いで丁寧に解説している。本書の各説にはKey Questionが立てられ、多くのExerciseを解答することで理解が深まるように構成されている。定型表現の用例も非常に多く、英語論文を執筆するときに参考になり有益である。
⑥A・L・ビーチ、M・D・ソルチネリ、A・E・オースティン、J・K・リヴァード著、林透・深野政之・山崎慎一・大関智史訳(2020)『エビデンスの時代のFD:現在から未来への架橋』東信堂
◇選定理由(抜粋
本書は、FD活動および各大学のFD推進組織の、これまでの到達点と今後の課題をまとめており、大学教育関係者、特にFD推進組織に在籍する教職員にとって貴重で重要な知見を提供するものとなっている。特にはアメリカにおけるFDの歴史・現状・課題を包括的かつ体系的に説明しており、FDの全体像を示している点を評価できる。また、現在手薄なFDの分野、および今後重要となるFDの分野について触れており、個別大学におけるFDプログラム開発の参考になる。さらに、FDのプログラム評価、研究対象としてFDを捉えた場合のその手法についても知見を提供している。総合的にみて、特に大学教育センター等に所属する教職員にとって、FDの歴史を確認し、先進国と見なしうるアメリカにおける実態と課題を知り、日本における課題や展望を考えるための基礎資料としては有益なもの。
⑦谷美奈著(2021)『「書く」ことによる学生の自己形成:文章表現「パーソナル・ライティング」を通して』東信堂
◇選定理由(抜粋
文系理系を問わず、アカデミック・ライティングに関する議論を扱う書籍が多い中、パーソナル・ライティングというライティングの新たな分野を拓く良著である。また、アメリカのPersonal Writingの歴史を踏まえつつ、パーソナル・ライティングとの比較を丁寧に記述していることや、パーソナル・ライティングの意義に関して学生にとって必要な自己形成との関連性を論じていること、そして具体的な教育実践の内容も詳述されてことにより、学生の自己形成を促す指導について悩んでいる読者にとって、その授業実践の改善に資するものとなる。総合的にみて、新たな議論の端緒として、また多様化した学生の課題のいくつかを解決するための実践事例として、本書の知見は有効であると考えられる。
⑧園山大祐編著(2021)『フランスの高等教育改革と進路選択:学歴社会の「勝敗」はどのように生まれるか』明石書店
◇選定理由(抜粋
本書は、フランスにおける高等教育改革について日本とフランスの若手からベテランの学者19名による14の論稿からなる書である。フランスの高等教育における、大学入学前後の実態や課題、新自由主義的な改革と選抜制度の課題、大学と階層移動やエリートの形成・選抜過程に関わる状況など、近年のフランスの高等教育の現状と課題に関する、多様な観点からの量的・質的な分析成果がまとめられている。フランスの大学教育を中心に、高大社連携の視点から、外からは見えにくい教育体制や法令的背景に至るまでしっかり踏まえてフランスの教育が紹介されており、フランスの大学教育研究を進めようとする者にとっては必読の書に位置づけられるばかりでなく、そのアプローチは、日本の大学教育研究など広く応用可能なものであり、フランスの高等教育政策や高等教育現場の状況や課題等の理解に役立つのはもとより、日本とは異なるフランスの制度や状況との比較を通した、日本の状況と課題の考察にも資する書となっている。
JACUEセレクション2021(2020年度認定図書)
①ジョセフ・E・アウン著、杉森公一、西山宣昭、中野正俊、河内真美、井上咲希、渡辺達雄共訳(2020)『ROBOT-PROOF:AI時代の大学教育』森北出版
◇選定理由(抜粋
ロボット・プルーフとはロボットに仕事を奪われない「耐ロボット性」をさす。そのような卒業生を輩出する、人工知能時代の高等教育の在り方のひとつは、人間に特有な創造性と柔軟性の育成であり、経験学習が効果的である。筆者が学長をつとめるノースイースタン大学のコーオプ教育(教室での学習と長期の職場経験を交互に行って統合する)が紹介されている。もうひとつは生涯学習の継続であり、生涯学習需要の増大と多様化に対応する国内外の大学間連携が、高等教育の進化における次の段階であるとする。産業や科学技術の発展などの歴史的変遷を丁寧に整理しつつ、現在の社会的状況を鋭く考察して、人工知能時代に求められる大学教育の在り方について具体的に言及している。コロナ禍における大学教育の在り方の議論に対しても有効な知見を提供している。
②大西好宣著(2020)『海外留学支援論:グローバル人材育成のために』東信堂
◇選定理由(抜粋
「グローバル人材」に関する多面的な考察、短期留学及びその効果測定の方法に関する批判的考察、アジア留学の意義などについて、多くの文献やデータに基づいてコンパクトにまとめられている。とても読みやすい。留学生理念モデルについて著者独自の修正が提案されており、終章では留学支援専門職育成のためのケースメソッドの事例が紹介されている。
③細尾萌子、 夏目達也、 大場淳編著(2020)『フランスのバカロレアにみる論述型大学入試に向けた思考力・表現力の育成』ミルネヴァ書房
◇選定理由(抜粋
約200年の歴史を持つフランスの大学入学資格試験であるバカロレアについて、その内容や評価方法、またバカロレアに至るまでの初等中等教育を丁寧にひもとき、日本への示唆を引き出している。中等教育段階での思考力・表現力の育成を大学入試においてどのように評価するか、また大学教育ではどういう教育的課題が残されているかという問題について、客観的な資料やデータに基づく科学的アプローチにより批判的に検討している。日本の大学入試、また高大接続改革の観点からも大学人の参考書となりうる。
④エリザベス・F・バークレイ、 クレア・ハウエル・メジャー著、 東京大学教養教育高度化機構アクティブラーニング部門、 吉田塁監訳(2020)『学習評価ハンドブック : アクティブラーニングを促す50の技法』東京大学出版会
◇選定理由(抜粋
Finkが提唱した「意義ある学習分類」に基づいて、50の学習評価技法が多くの事例とともに6つの領域にまとめられている翻訳書。各章の内容が構造化されており、個々の学習評価技法が、概要・学習目的・実施方法・活用例・参考文献などの項目に沿って記されている。50の学習評価技法それぞれに、オンラインで実施するための工夫や教室での授業とオンライン授業の事例が記されており、遠隔授業をサポートする視点でも有用と考えられる。
JACUEセレクション2020(2019年度認定図書)
①藤本昌代・山内麻理・野田文香編著(2019)『欧州の教育・雇用制度と若者のキャリア形成‐国境を越えた人材流動化と国際化への指針‐』白桃書房
◇選定理由(抜粋
本書は、大学生を含めた若者の雇用・就職、キャリア形成支援に関する制度・政策、および関連する学生の取組を正面にすえて、高等教育のあり方を論じたものである。本書の内容は、日本と同様に政府主導型の制度の導入が行われているとされる欧州の教育制度、雇用制度、入職後のキャリア等をめぐる動向を理解し、国ないし広域圏レベルの政策形成や制度構築についての示唆を得るとともに、日本の課題を浮き彫りにする上で貴重な資料となり得るものである。
②山田礼子(2019)『2040年 大学教育の展望‐21世紀型学習成果をベースに‐』東信堂
◇選定理由(抜粋
本書は、ここ20年の社会変革を背景とした大学教育の改革のプロセスを俯瞰的視野と具体性の双方の視点をもって丁寧に記述するとともに、知識基盤社会に向けた今後の20 年の大学の在り方について明確な方向性を提示するものである。内容は、学生の「主体的に学ぶ力」の獲得という視点をベースに、グローバル・コンピテンシー習得につながるカリキュラムや教授法の工夫、学修成果を基盤とした教学マネジメントなど多様であり、大学の執行部をはじめ多くの大学関係者に、是非手に取ってもらいたい本である。
③濱名篤(2018)『学修成果への挑戦‐地方大学からの教育改革』東信堂
◇選定理由(抜粋
本書は、近年の文教政策と絡ませながら学士課程教育における実践的な課題を網羅的に論じたものである。学士課程における学修成果を核にした教学マネジメントについて、私学経営者としての経験を踏まえて明確に述べられている。今後、高等教育研究を志す者や、大学教職員が自らの大学改革を検討する際に、近年の高等教育政策の動向を知る上で有益な書である。
④関西国際大学編(2018)『大学教学マネジメントの自律的構築‐主体的学びへの大学創造20年史‐』東信堂
◇選定理由(抜粋
本書は、関西国際大学における20 年間の先駆的な教育改革の取り組みについて4つの時期にわたって詳細にまとめられたものである。本書は、大学教育の今日的課題に対して、全学FDによる組織的な教育改革を軸としてアクティブラーニングやeポートフォリオ評価、学習支援型IRといった様々な方法を導入・推進していく過程が事細かく描かれており、FD・SD・IR・大学組織開発者にとってのリファレンスともなる一冊である。

