-

会員管理システム

会員管理システム
-
会員管理システムでは、次の機能がご利用いただけます。
・会員情報の照会・更新
・会費納付状況
・会誌発送状況
・パスワード変更
・オンライン名簿・会員検索システム
・オンラインクレジット決済システム
-
会員管理システムでは、次の機能がご利用いただけます。
-

学会を知る
-

イベントに参加する

イベントに参加する
-

活動にふれる

活動にふれる
-
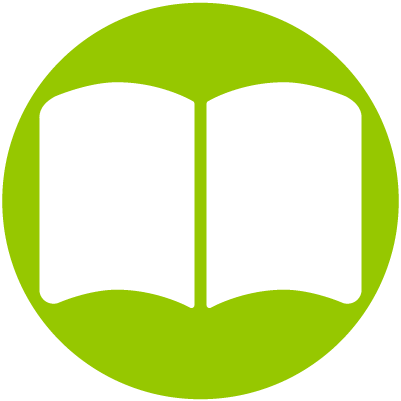
出版物を見る
査読についての内規
2016年3月26日 大学教育学会誌編集委員会決定
2017年6月30日 大学教育学会誌編集委員会改正
2022年5月14日 大学教育学会誌編集委員会改正
この内規は、大学教育学会誌編集委員会規程第7条に基づく原稿の査読について実施上必要な事項を定める。
1. 査読者の決定
1-1.【査読者の選定】査読者については、編集会議が原稿ごとに適任者を選定する。なお、編集委員の中から筆頭査読者を1名選定する。(投稿締切日より1週間を目処とする)
1-2.【査読者の人数】査読者の人数は論文等の区分に応じ、次のとおりとする。
①「研究論文」 3名(編集委員2名、指名査読者1名)
②「事例研究論文」 3名(編集委員2名、指名査読者1名)
③「展望・総説論文」 3名(編集委員2名、指名査読者1名)
④「ラウンドテーブル報告」 1名(編集委員)
1-3.【査読者の匿名性】原稿ごとの査読者の氏名は編集委員会外では匿名とする。
2. 査読の実施
2-1.【「論文」の査読】「論文」の査読者は「投稿倫理に関する申し合わせ」と下欄にある観点に基づいて行われた評価を参考に、次に示す査読結果のいずれに当たるかを決定する。
A. 採録
B. 修正採録
C. 修正再査読
D. 不採録
|
観点1:独創性・新規性(論文が大学教育研究に新しい知見を提供していること) a:従来の研究とは異なる発想により、極めて独創的な知見を提供している b:従来の研究の到達点を更新する、新規性を有した知見を提供している c:従来の研究から容易に予測されるものの、一応新しい知見を提供している d:必ずしも新しい知見を提供しているとは言えない 観点2:有用性(得られた知見が大学教育の改善や発展に有益であること) a:得られた知見が大学教育の改善や発展に極めて有益である b:得られた知見が大学教育の改善や発展に有益である c:得られた知見が大学教育の改善や発展に一部有益である d:得られた知見が大学教育の改善や発展にほとんど有益でない 観点3:先行研究への言及(必要かつ十分な先行研究に言及していること) a:国内外で発表された先行研究について幅広く言及し、適切に位置づけている b:国内外で発表された先行研究について広く言及している c:限られた先行研究のみに言及している d:先行研究への言及が乏しい 観点4:一貫性(設定された問いと結論が対応しており、適切な研究方法が選択されていること) a:問いと結論の対応および研究方法のどちらも申し分ない b:問いと結論の対応ないし研究方法のいずれかに修正の余地がある c:問いと結論の対応および研究方法のいずれにも修正の余地がある d:問いと結論が対応していない、もしくは適切な研究方法が選択されていない 観点5:形式(投稿要領が遵守されており、文章が明快であること) a:形式的な面で問題はなく、投稿原稿をそのまま学会誌に載せることができる b:軽微な修正を施せば、形式的には学会誌に載せられる水準である c:学会誌に載せるには、形式的な面で大幅な修正が必要である d:投稿要領が十分理解されていない *なお、研究論文の場合は観点1、事例研究論文の場合は観点2、展望・総説論文の場合は観点3の得点を重視するものとする |
2-2.【「報告」の査読】「ラウンドテーブル報告」の査読者は、「投稿倫理に関する申し合わせ」とラウンドテーブルの趣旨に配慮しつつ、査読結果が前項にある4段階のいずれに当たるかを決定する。
2-3.【査読結果の提出】査読者は査読結果と投稿原稿の優れている点および改善を要する点を所定の様式にまとめ、編集委員会に提出する。(投稿締切日より4週間を目処とする)
2-4.【採否判定】筆頭査読者は、他の査読者と協議の上、査読結果を総合し、各原稿について「採録」「修正採録」「修正再査読」「不採録」の4段階による採否判定を行う。投稿倫理違反を理由とする不採録の場合は、その旨別途、編集会議に報告する。
3. 採否判定の通知
3-1.【通知】編集委員長は、採否判定を投稿者に通知する。その際、査読者からの査読結果とコメントを合わせて投稿者に知らせるものとする。(投稿締切日より6週間を目処とする)。なお、通知文書は筆頭査読者が作成する。
3-2.【修正採録】「修正採録」の判定を受け取った投稿者は、査読コメントにそって修正を行った上で返送する。返送された原稿は、当初の査読者によって適切な修正が行われていることを確認の上、「採録」とする。(投稿締切日より8週間を目処とする)
3-3.【修正再査読】「修正再査読」の判定を受け取った投稿者は、査読コメントにそって修正投稿を行うことができ、修正投稿された原稿は、当初の査読者により再査読される。筆頭査読者は、他の査読者と協議の上、「採録」か「不採録」かの最終採否判定を行う。最終採否判定結果は、編集委員長から投稿者に通知する。(投稿締切日より11週間を目処とする)
4. 査読内規の変更
この内規の変更は、編集委員会が行うものとする。

